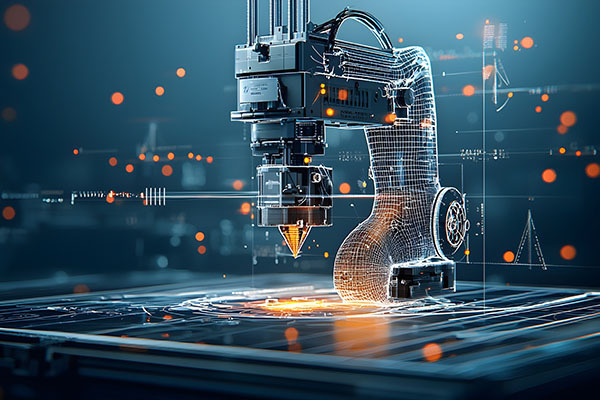
製造業界では近年、従来の切削加工とは全く異なるアプローチで製品を作る付加製造技術が普及しています。
この技術は3Dプリンティングとしても知られ、試作品開発から最終製品まで幅広い分野で活用が進んでいるのです。
特に複雑な形状の部品製造や小ロット生産において、その真価を発揮しています。
自動車、航空宇宙、医療機器などの業界では、従来では不可能だった軽量化や機能統合を実現し、製造コストの削減と開発期間の短縮を同時に達成しました。
一方で、付加製造技術の導入には専門知識の習得や品質管理体制の構築が欠かせません。
この記事では、付加製造技術の7つの方式や導入メリット、実際の活用事例を詳しく解説し、成功する導入ステップと注意すべきポイントも紹介していきます。
目次
付加製造技術とは?
付加製造技術とは、材料を少しずつ積み重ねながら立体的な製品を作り上げる製造方法です。
英語では「Additive Manufacturing(AM)」と呼ばれ、日本では一般的に3Dプリンティングという名前で親しまれています。
従来の切削加工が材料を削って形を作るのに対し、付加製造技術は材料を付け足していく点が大きな特徴といえるでしょう。
この技術は2020年にJIS規格B9441として正式に規格化され、「3Dモデルデータをもとに、材料を結合して造形物を実体化する加工法」と定義されました。
具体的にはコンピューターで作成した3次元の設計図をもとに、樹脂や金属などの材料を薄い層状にして順番に積み上げます。
現在では試作品開発から最終製品まで、幅広い分野で活用が進んでいます。
ASTM規格による付加製造7方式の特徴

ASTM規格による付加製造の方式として、以下7つの方式があります。
- 材料押出
- 材料噴射
- 結合剤噴射
- 液槽光重合
- 粉末床溶融結合
- 指向性エネルギー堆積
- シート積層
順番に特徴を見ていきましょう。
方式1:材料押出
材料押出法は、一般的にFDM(熱溶解積層法)として知られるもっともポピュラーな付加製造技術です。
この方式では、熱可塑性樹脂のフィラメントを高温で溶かし、ノズルから押し出して一層ずつ積み重ねます。
ABSやPLA、PEEKなどの工業用樹脂が使用でき、試作品から最終製品まで幅広い用途で活用されています。
導入コストが比較的安価で操作も簡単なため、製造業の現場でも取り入れやすい技術といえるでしょう。
方式2:材料噴射
材料噴射法は、インクジェットプリンターの技術を応用した高精度な付加製造技術です。液状の光硬化性樹脂やワックスを、まるでインクのように微細な液滴として噴射し、すぐに紫外線で硬化させます。
この方式の最大の特徴は、複数の材料を同時に使用できることです。
例えば、モデル材とサポート材に異なる材料を使用したり、カラー表現や異なる物性を組み合わせた部品製造が可能になります。精密で美しい仕上がりが期待できるため、試作品や展示用モデルの製作に重宝されています。
方式3:結合剤噴射
結合剤噴射法は、粉末材料に液体の接着剤を選択的に噴射して固める革新的な技術です。砂で城を作るときに水をかけて固めるように、金属やセラミック、石膏などの粉末に結合剤を吹き付けて形を作ります。
この方式の優れた点は、サポート材が不要で、周りの粉末が自然な支えとなることです。また結合剤に着色料を混ぜることで、フルカラーの立体物も製造できます。
造形後に焼結処理や含浸処理を行うことで、より強度の高い最終製品に仕上げることも可能です。
方式4:液槽光重合
液槽光重合法は、光造形やSLA(Stereolithography)として親しまれている精密造形技術です。
タンクに入れた液状の光硬化性樹脂に、レーザーや紫外線を照射して一層ずつ硬化させていきます。
写真の現像のように、光が当たった部分だけが固まる仕組みを活用した画期的な製造方法なのです。表面が非常に滑らかで精密な仕上がりになるため、医療器具や宝飾品、精密部品の製造に適しています。
ただし、使用できる材料が光硬化性樹脂に限られるため、金属部品の製造には向いていません。
方式5:粉末床溶融結合
粉末床溶融結合法は、レーザーや電子ビームを使って金属や樹脂の粉末を溶融結合させる高度な技術です。
SLS(Selective Laser Sintering)やSLM(Selective Laser Melting)とも呼ばれ、航空宇宙産業で特に注目されています。平らに敷き詰めた粉末材料に集中的な熱エネルギーを加え、まるで溶接のように粒子同士を結合させます。
この方式では、従来の加工法では不可能な中空構造や複雑な内部形状も実現できるのです。
チタンやアルミニウムなどの高機能金属部品を直接製造できるため、医療機器や自動車部品の製造で活用が広がっています。
方式6:指向性エネルギー堆積
指向性エネルギー堆積法は、レーザーデポジションやLMDとも呼ばれる金属加工に特化した技術です。
- レーザー
- 電子ビーム
- プラズマアーク
などの高エネルギー源で金属粉末やワイヤーを溶融し、肉盛溶接のように積み上げます。
まるで職人が鍛冶で鉄を叩いて形を作るように、熱エネルギーで材料を溶かしながら自由自在に形を作り上げるのです。
既存の部品に新たな機能を追加したり、摩耗した部分を修復したりする用途でも活用されています。
大型の金属部品製造や修理・メンテナンス分野で、その真価を発揮する技術といえるでしょう。
方式7:シート積層
シート積層法は、
- 紙
- 樹脂
- 金属箔
などのシート材料を積み重ねて立体物を作る独特な技術です。
まるで切り絵を何層にも重ねるように、各層を断面形状に切断してから接着や溶接で結合していきます。
この方式の魅力は、フルカラーの立体モデルや複数の異なる材料を組み合わせた製品を作れることです。紙を使用すれば環境に優しく、コストも抑えられるため、建築模型や教育用途での活用が進んでいます。
金属箔を使用した場合には、導電性を持つ電子部品の製造も可能になる画期的な技術なのです。
付加製造技術を導入する3つのメリット
付加製造技術を導入するメリットとして、以下の3つがあげられます。
- コスト削減と短納期化
- デザインの自由度向上
- 在庫管理の効率化
順番に解説していきます。
メリット1:コスト削減と短納期化
付加製造技術の最大の魅力は、製造コストと開発期間を大きく短縮できる点です。従来の製造方法では、試作品を作るために高額な金型を製作する必要がありましたが、付加製造技術では3Dデータがあれば直接造形できます。
また金型製作に数週間から数ヶ月かかっていた工程が、数時間から数日に短縮されるため、製品開発のスピードが格段に向上します。
特に試作や小ロット生産において、付加製造技術は企業の競争力強化に大きく貢献するのでしょう。
メリット2:デザインの自由度向上
付加製造技術は、従来の切削加工では実現不可能な複雑な形状を造形できる特徴を持っています。切削工具が入らない中空構造やオーバーハング形状、さらには格子状の内部構造まで一体成形で製造可能です。
従来であれば複数の部品を組み合わせて作る必要があった製品も、付加製造技術なら一つの部品として製造できるため、部品点数の削減と組み立て工程の簡素化を同時に実現できます。
この技術により、製品の軽量化や機能の最適化も可能になり、航空宇宙産業や医療分野では画期的な設計が次々と生まれているのです。
たとえば、内部に冷却チャンネルを持つ金型や、患者一人一人に合わせたカスタム医療機器などが実用化されており、従来の製造技術では考えられなかった高機能製品の開発が進んでいます。
メリット3:在庫管理の効率化
付加製造技術の導入により、製造業の在庫管理効率化も期待できます。
従来の大量生産では、将来の需要を予測して大量の部品や製品を事前に製造し、倉庫に保管する必要がありました。
しかし、付加製造技術では必要な時に必要な量だけを製造できるため、過剰在庫のリスクを大幅に軽減できます。特に需要変動が激しい製品や、カスタマイズが必要な製品では、オンデマンド製造の恩恵は計り知れません。
さらに、デジタルデータとして部品情報を保存できるため、世界中のどの工場でも同じ部品を製造可能になり、グローバルなサプライチェーンの効率化にも貢献します。
製造拠点を分散させたり、部品の緊急調達が必要になったりした場合でも、データ転送により迅速な対応が可能です。
中小企業にとっては、小ロット生産や多品種生産への対応力が飛躍的に向上し、ニッチな市場でも効率的に事業展開できるようになるのです。
付加製造技術の導入事例3選
ここからは実際に付加製造技術を導入した企業の実例を紹介していきます。
順番に見ていきましょう。
事例1:自動車産業での金型製造による開発期間短縮
自動車部品を製造するある企業では、金属部品の成形に使用する金型製作に付加製造技術を導入しました。金型とは、金属を決まった形に成形するための型のことで、従来は切削加工により数週間から数ヶ月かけて製作していました。
しかし、付加製造技術の導入により、金型の製作期間とコストを大幅に削減できるようになったのです。特に試作段階では、設計変更が頻繁に発生するため、短期間で金型を製作できることは大きなメリットでした。
また、付加製造技術により内部に冷却チャンネルを設けた高性能な金型も製作できるようになり、成形サイクル時間の短縮も実現しました。
事例2:電子機器製造における治具製作による品質向上の実現
大型の電子機器を製造するある企業では、組み立て作業で発生する部品の取り間違いや組み立てミスが深刻な課題でした。
この問題を解決するため、付加製造技術を活用して作業用の「治具」を製作し、生産プロセス全体を見直し。従来は金属や木材で作られていた治具を、付加製造技術によってプラスチック材料で短期間かつ低コストで製作できるようになりました。
この治具により、作業者が間違った部品を取ることがなくなり、組み立て作業の精度が飛躍的に向上したのです。
結果として、月間で発生していた不具合件数を大幅に削減し、製品の品質向上と作業効率化を同時に達成できた好事例です。
事例3:航空宇宙産業での複雑部品一体成形による軽量化達成
航空宇宙産業のある企業では、ジェットエンジンの燃料ノズル製造に付加製造技術を導入し、画期的な成果を上げました。
従来の製造方法では複数の部品を組み合わせて作っていた燃料ノズルを、付加製造技術により一つの部品として一体成形できるようになったのです。
この技術革新により、部品の大幅な軽量化を実現し、同時に複数の小さな部品を一つにまとめることで組み立て工程も簡素化されました。
さらに、内部に複雑な冷却チャンネルを設計できるようになったため、部品の耐久性と性能も向上しています。
付加製造技術を導入するまでの6ステップ
付加製造技術導入までの手順は、以下の6ステップに分けられます。
- 目的と要件の明確化
- 技術方式の選定
- 設備と材料の検討・選定
- 段階的導入計画の策定
- 3Dデータ準備と人材育成
- 実証実験と効果検証
順番に解説していきます。
ステップ1:目的と要件の明確化
付加製造技術導入の第一歩は、なぜ導入するのかという目的を明確にすることです。
- 試作品開発の短縮化を目指すのか
- 複雑形状部品の製造を実現したいのか
- 小ロット生産に対応したいのか
などによって、選択すべき技術や設備が大きく変わります。
具体的には、製造する部品の材質や必要個数、納期などの条件の整理です。
また従来の切削加工や成形加工を完全に置き換えるのか、それとも補完的な役割として活用するのかを決定しなければなりません。
導入後の運用体制や保守管理についても、この段階で検討しておくと後の工程がスムーズに進みます。
ステップ2:技術方式の選定
目的と要件が明確になったら、付加製造方式から最適な技術を選択します。
たとえば樹脂部品であれば、材料押出や液槽光重合が候補となり、金属部品なら粉末床溶融結合や指向性エネルギー堆積が有力な選択肢になるでしょう。また表面仕上げの品質を重視する場合は、材料噴射や液槽光重合が適しており、大型部品の製造にはシート積層や結合剤噴射が向いています。
各技術方式には得意分野と制約があるため、製造する部品の特性と技術の特徴を照らし合わせて判断することが重要です。
また材料の入手しやすさや装置の価格帯も、選定の重要な要素となります。
複数の技術方式を比較検討し、費用対効果を含めた総合的な評価を行うべきでしょう。
ステップ3:設備と材料の検討・選定
技術方式が決定したら、具体的な装置選定と材料検討に進みます。
付加製造装置は、
- 精度
- 造形サイズ
- 材料対応範囲 によって価格が大きく異なるため、要求仕様を満たす最適な機種を選ぶ必要があります。
装置導入に伴う設置環境の整備も重要な検討事項で、
- 電力容量
- 換気設備
- 安全対策
などを事前に準備しなければなりません。
材料については、目的に応じた機械的性質や加工性を持つものを選定する必要があります。
金属粉末を使用する場合は、粒度分布や純度が造形品質に大きく影響するため、信頼できる材料メーカーからの調達が重要です。
また材料の保管方法や安全な取り扱い手順についても、導入前に十分な準備が必要となります。
ステップ4:段階的導入計画の策定
付加製造技術の導入は、リスクを最小化するために段階的にアプローチするとよいでしょう。
第1段階では工法のみを変更し、既存の設計をそのまま付加製造で製作して技術習得を図ります。
第2段階では軽微な設計変更を加え、付加製造技術の特徴を活かした改良を。
第3段階では積極的な設計変更を行い、従来の製造法では実現できない高機能部品の開発に挑戦します。
各段階で得られた知見と経験を次の段階に活かしながら、徐々に技術レベルを向上させていく計画が効果的です。
導入スケジュールは無理のない範囲で設定し、各段階での評価基準も明確に定めておくことが成功の鍵となります。
ステップ5:3Dデータ準備と人材育成
付加製造技術の運用には、高品質な3DCADデータの作成技術が不可欠です。
従来の2次元図面とは異なり、立体的な形状データを正確に作成する必要があるため、CADソフトウェアの習熟が重要になります。
造形用のデータ変換作業も専門知識が必要で、スライスデータの作成や造形パラメーターの設定には経験とノウハウが求められます。
また装置の操作や保守管理についても、専門的な知識を持った人材の育成が必要です。
外部研修の受講や装置メーカーによる技術指導を活用し、社内での技術伝承体制の構築が重要です。
ステップ6:実証実験と効果検証
導入準備が整ったら、実際の製品を用いた実証実験を実施します。
まずは比較的単純な形状の部品から始めて、造形品質や寸法精度を評価することが大切です。従来の製造方法と比較した場合のコスト効果や納期短縮効果についても、具体的なデータを収集して定量的に評価する必要があります。
品質面では、機械的性質や表面性状、耐久性などを総合的に検証し、実用に耐える品質が確保できるかを確認しましょう。問題が発見された場合は原因を分析し、造形条件や後処理方法の改善を図ります。
実証実験の結果を踏まえて本格導入の可否を判断し、必要に応じて計画の見直しを行うことで、確実な技術定着を図ることができます。
付加製造技術導入時の3つの注意点
付加製造技術導入時の注意点としては、以下の3つがあげられます。
- 専門知識と技術習得の必要性
- 導入・運用コストの検証
- 品質管理と後処理の課題
順番に見ていきましょう。
注意点1:専門知識と技術習得の必要性
付加製造技術の導入でもっとも重要な注意点は、専門的な知識と技術の習得が不可欠であることです。
従来の製造業とは大きく異なる技術であるため、単純に装置を導入するだけでは効果的な活用はできません。3DCADデータの作成技術をはじめ、スライスデータの変換や造形パラメーターの設定など、多岐にわたる専門知識が求められます。
特に金属3Dプリンターでは、造形パラメータが適切でなければ粉末の溶融・固化が不十分となり、空隙などの欠陥が発生する可能性があります。現在、多くの大学や教育機関が付加製造に特化したコースを開講していますが、実践的な経験が業界の成長に完全に追いついていない状況です。
注意点2:導入・運用コストの検証
付加製造技術の導入では、経済性の慎重な検証が欠かせません。
初期投資は装置本体だけでなく、設置環境の整備や安全対策なども含めると高額になる可能性があります。特に部品を仕上げるために必要なすべての後処理作業を考慮すると、想定以上のコストが発生する場合があります。
また、付加製造に使用される材料のコストも相当なものになるため、費用対効果を十分に検討する必要があります。
造形後の精度によっては別途加工が必要になるケースもあり、加工のための追加費用が発生すると導入効果が大きく損なわれる恐れがあります。
一方で、より大型で高速な機械の導入により全体的な経済性が向上していることから、段階的な導入計画を立てて慎重に進めることが重要です。
注意点3:品質管理と後処理の課題
付加製造技術では、従来の製造方法とは異なる品質管理体制の構築が必要になります。品質に影響する要因は多岐にわたり、材料の管理から造形条件、環境条件まで総合的な品質確認項目の整備が求められるのです。
造形後には表面処理や熱処理などの後加工が必要になることも多く、これらの工程も品質に大きく影響します。特に金属部品では、造形パラメータの最適化や造形後の熱処理改良による特性向上が課題となっています。
品質保証基準についても、従来の大量生産時の基準から付加製造用の基準への見直しが必要で、社会導入に向けた段階的なアプローチが重要です。
付加製造技術の今後の展望
付加製造技術は今後、製造業全体を変えていく画期的な技術として成長が見込まれています。
3Dプリンティング市場は2025年から2033年にかけて18%という高い成長率で拡大すると予測されており、特に金属材料分野では2030年までに数十億ドル規模の市場に達する見込みです。
技術面では、高機能な3Dプリンターが手頃な価格で提供されるようになり、従来は大企業だけが活用できた技術が中小企業や個人レベルまで普及していきます。
さらに注目すべきは、3Dプリンティングと従来の切削加工を組み合わせたハイブリッド製造技術の台頭で、材料効率と設計の柔軟性を両立させた革新的な製造方法が実現されつつある点です。付加製造技術は単なる試作ツールから、実際の製品製造を担う重要な技術へと進化を続けています。
まとめ
付加製造技術は、材料を積み重ねて立体製品を作る革新的な製造方法で、3Dプリンティングとして親しまれています。
ASTM規格では以下7つの製造方式が定義されており、用途に応じた選択が可能です。
| 方式 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 材料押出 | 樹脂フィラメントを溶融積層 | 試作品・教育用 |
| 材料噴射 | インクジェット技術応用 | 精密モデル・カラー造形 |
| 結合剤噴射 | 粉末に接着剤を噴射して固化 | フルカラー造形・セラミック部品 |
| 液槽光重合 | 光硬化樹脂をレーザー硬化 | 医療器具・宝飾品 |
| 粉末床溶融結合 | 金属粉末をレーザー溶融 | 航空宇宙・医療機器 |
| 指向性エネルギー堆積 | レーザーで金属を溶融堆積 | 大型金属部品・修理用途 |
| シート積層 | 薄いシートを積層接着 | 建築模型・電子部品 |
付加製造技術の導入メリットは次の3点です。
- コスト削減・短納期化
- デザイン自由度向上
- 在庫管理効率化
自動車業界では金型製作期間の大幅短縮、航空宇宙分野では燃料ノズルの軽量化など、実用的な成果が生まれています。
導入時は専門知識の習得、運用コストの慎重な検証、品質管理体制の構築が重要です。
2025年以降、市場は年18%の高成長が予測されており、製造業の競争力強化に欠かせない技術として普及が加速するでしょう。
